個々のスペック、多様な価値観、なりたい自分、なれない自分。
全てを受け入れ尊重し合い、障がいという概念を無くことで心理的安全性のある社会を築く。
「といろ」は障がいのあるお子さまのための『児童発達支援』『放課後等デイサービス』を行っている多機能型療育施設です。
といろでは苦手を克服させる強制的な支援ではなく、お子様の得意や好きを伸ばすことで、一人ひとりの自信に繋げる為の支援に力を入れています。
活動を通して個々の興味、関心を最大限に広げ、好きや得意等の強味を見つけ一人ひとりに寄り添い、自己肯定感を阻害せず社会と向き合っていけるマインドを育みお子様の可能性を最大限にひろげていきます。

運動療育を行う4つの目的
1.協調運動の発達を促すため
発達障害児の中には、感覚の協調を苦手とする子が多くいます。日常生活の中には感覚の協調を必要とする事が多く、目から見た情報と体の動きを協調させたり、左右の手の動きを協調させたりすることも必要です。
健常児が無意識で出来ている、感覚と行動の協調は一部の発達障害児には大変難しい行動であることが少なくありません。
運動療育を通して、感覚や行動の協調を学ぶことも目的のひとつです。
感覚や行動の協調は日常生活や運動以外に、勉強などにも必要です。
鉛筆を握って字を書く際、視覚で字を書く位置やバランスを確認しつつ指先で鉛筆をコントロールし、書きたい文字を脳で考えて字を書きます。運動療養によって感覚や行動の協調がスムーズに行えるようになると、学習意欲が向上することもあるでしょう。
2.自分の体のコントロール方法を学ぶため
運動療養によって、自分自身の体をコントロールする能力を身に付ける目的もあります。発達障害を持つ子どもの中には、力のコントロールを苦手とする子が少なくありません。
運動療法を通じて、自分自身の体のコントロール方法を学び、自分自身のイメージとパワーコントロールのズレを減らすことも期待されます。
3.自己肯定感を高めるため
発達障害児の多くは健常児と共に過ごしています。一般の保育園や幼稚園に通いながら療育を行う子どもや、小学校では通常級と特別支援級を併用するケースも多いからです。
その中で、コミュニケーションが上手くとれないことや、健常児と同じ事をできないという失敗経験を積みやすいのが大きな問題となっています。
失敗を繰り返すことで自己嫌悪や自己否定を起こしてしまったり、他人と上手く関われないことで消極的になってしまうケースもあるでしょう。
運動療育では「できた」という自己肯定感の向上を目的とする一面もあります。運動には多種多様なものがあり、勝敗にこだわるものばかりではありません。机に座って行う学習に比べると、プログラムの内容を慎重に考えれば「できない」を限りなく減らすことも可能です。
子ども自身が持つ療育へのモチベーションを高め、自信をつけさせる際にも運動療育は適していると言えるでしょう。
4.ストレスを発散するため
発達障害児の中には多動性や衝動性などの特性を持ち、じっとしている事を苦手とする子ども達も少なくありません。そんな子ども達にとって着席して机に向かって行う療育は、多かれ少なかれストレスになることもあるでしょう。
子ども達のストレスを発散させる意味でも運動療育が取り入れられています。
運動療育で充分に体を動かしてからパワーを発散させてから学習療育を行ったり、頑張って着席して療育に取り組んだご褒美として楽しく体を動かす運動療育を行うなど、子どもにとってできる限りストレスを減らしながら療育を行うためにも大切なプログラムです。
運動療育の効果
一般の保育園や幼稚園、学校などでも、外遊びや体操、体育などの授業はつきものです。子どもの発達にとって運動は欠かせないものと言えます。療育でも、子どもの発達にとって運動が必要だという点は同じです。

【住所】
大阪府松原市天美南5丁目18−14
【営業時間】
平日:10時00分~19時00分
祝日:09時00分~18時00分
【サービス時間】
平日:11時00分~18時00分
祝日:10時00分~17時00分
【お休み】
土・日曜日
年末年始(12月31日~1月3日)

運動療育特化型
⼩集団での運動プログラムを通じて、運動⼒・
協調性・コミュニケーション能⼒を養います。

送迎サービスあり
事業所より車で30分圏内までの送迎があり、
送り迎えをしていただく必要がありません。
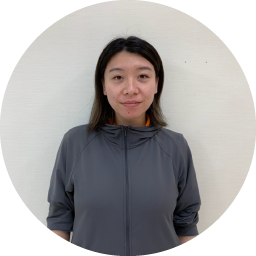
専門職の配置
⼀⼈ひとりの個性・特性・発達段階に
応じた課題を抽出し、個別療育を⾏います。
運動療育とは
発達障害を持つ子どもや、診断を受けるには至らない発達障害グレーゾーンに含まれる子ども達の中には、発達性協調運動障害を併せ持っているケースが多いです。
発達性協調運動障害とは、発達の早期から日常生活が困難なレベルの手先の不器用さや運動の苦手さが見られる障害です。子どもの5~6%に見られ、ハサミを使うことや紐を結ぶことなどを苦手とします。また、よく転んだり縄跳びなどの運動が極端にできないケースも少なくありません。
発達性協調運動障害を持っている子どもは運動に苦手意識を持っていたり、運動ができないことで自己否定に陥っていることが多くあります。そんな子ども達にとって運動療育は協調運動の基礎を培い自己肯定感の向上などの効果が期待できる療育です。

申請書をはじめ、各種手帳や医師などの意見書、身元が確認できる書類などをそろえ、市区町村に申請します。
【必要書類】1.医師の意見書 2.医師による診断書 3.療育手帳 4.障害者手帳
上記のいずれか一つがあれば申請が可能です。
申請時に必要な書類の一つに障害児支援利用計画案があります。障害児支援利用計画案は相談支援事業所で利用計画案の作成してもらえます。または、セルフプランとして保護者や支援者が利用計画案を作成することも可能です。自治体によってはホームページからフォーマットをダウンロードすることもできます。
見学・体験利用を経て、契約日数を調整。
利用開始・事業所と日程調整の上、利用開始となります。
といろ東住吉 自己評価・保護者等評価結果
【児童発達支援】自己評価結果総括表
【放課後等デイサービス】 令和6年度保護者等向けアンケート
【放課後等デイサービス】 令和6年度事業所における自己評価結果
【放課後等デイサービス】自己評価結果総括表
支援プログラム
といろ松原 自己評価・保護者等評価結果
【放課後等デイサービス】令和6年度 自己評価結果
【放課後等デイサービス】令和6年度 保護者評価結果



